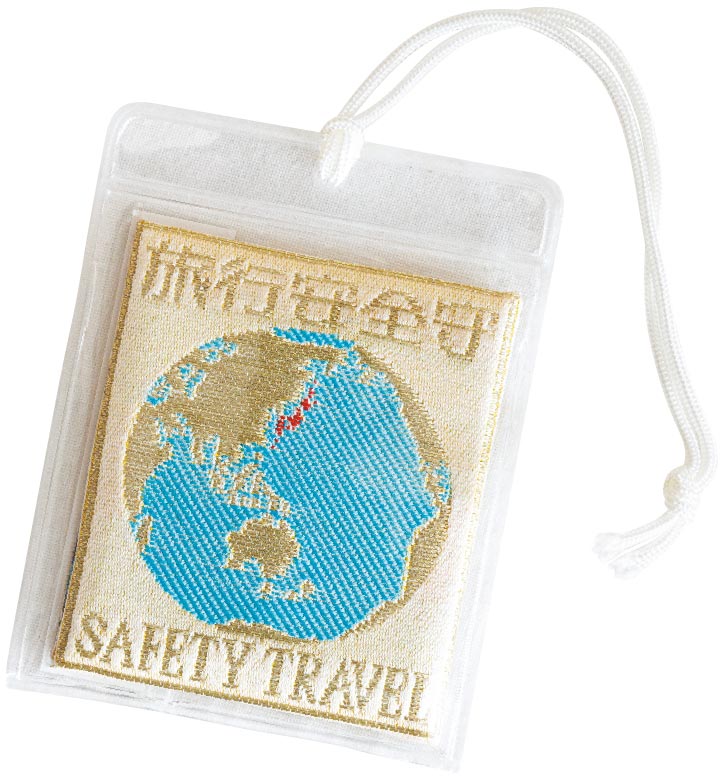2025 NO.37
Menu
 街歩きにっぽん
街歩きにっぽん
海外との交流で栄え、16世紀には自治都市を築き上げた。
豊かな文化と進取の気風は、いまも残されている。
写真●栗原 論, Aflo, PIXTA

堺旧港にたたずむ「旧堺燈台」
堺の地名は、かつての地方行政区分である摂津・和泉の「境」に位置したことに由来する。「方違神社」は河内を含めた三国の境界に立つことから、どの場所にも属さない、方位のない聖地として尊崇を集める。その南側には、4世紀後半から6世紀前半にかけてつくられた44基の墳墓から構成され、世界遺産に登録される「百舌鳥古墳群」が広がる。なかでも全長約486mの「大仙陵古墳(仁徳天皇陵古墳)」は、世界最大級の墳墓のひとつ。この地は、東にあった都への道が通る交通の要衝で、海外から多くの使者が行き交ったという。墳墓の雄大な姿は、国力の大きさを顕示する役割も担ったことだろう。

海外との交流で栄えた賑わいを今に伝える『南蛮屛風』(提供=堺市博物館)